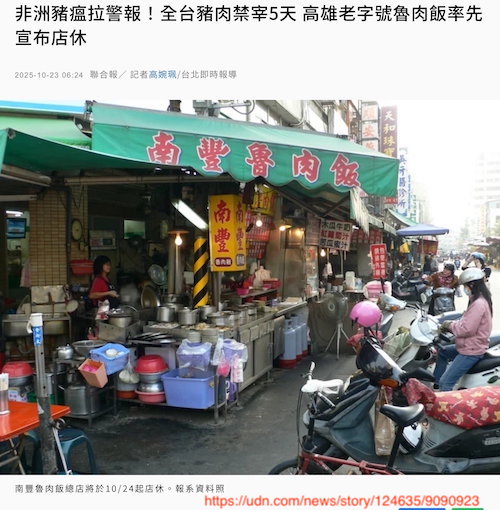海上保安庁 第11管区海上保安本部によると、尖閣諸島の接続水域を航行していた中国海警局の船2隻が10月19日午後に出域し、10月20日には確認されなかった。連続航行日数は、昨年(2024年)11月19日からの335日で途切れた。
10月18日までは4隻の中国海警局の船、「海警2502」「海警2307」「海警2305」「海警2302」が接続水域を航行していた。
10月18日午後7時頃、「海警2305」と「海警2302」が接続水域から出域した。AIS情報をみるとそのまま大陸沿岸まで戻っていた。
10月19日午後7時頃、残っていた「海警2502」と「海警2307」も接続水域から出域した。この2隻のAIS情報でも、そのまま大陸沿岸まで戻っていっていた。
数日間、AIS情報は発信されていなかった。しかし10月25日(土)朝にMarineTrafficを調べてみたところ、24日の午後には「海警2502」と「海警2307」が尖閣沖に来ていた。
(10月23日や24日朝に4隻を調べた時は、AIS情報は発信されていなかった。)
 (海上保安庁(pdf)より。10月23日時点。25日昼にスクリーンショット取得)
(海上保安庁(pdf)より。10月23日時点。25日昼にスクリーンショット取得)
中国海警局の船が尖閣諸島の沖からいなくなった理由として、マスメディアの記事ではもっぱら「荒天に伴って退避した可能性がある」という説明がされている。
たしかに10月20日頃から、台湾本島の北から北東の海は波高6メートル超の荒天となっていた。10月21日付け記事が書かれた段階では、その説明が確からしいように思える。
また、X(旧 Twitter)などSNSでは、高市早苗 自民党総裁が第104代首相に選出されたことと関連付けて「高市効果」といったコメントもあった。公明党や国土交通大臣を絡めたようなコメントも散見された。
これらの分析は後にまわすとして、当ブログ管理人は、悪天候に加えて、中国共産党の重要会議である四中全会も関係していた仮説を示してみたい。
四中全会(第20期中央委員会第4回全体会議)は10月20日から23日まで開催された。
中国海警局の船4隻は、四中全会が始まる直前の10月18日・19日に尖閣沖から退去して、中国大陸へと帰っていった。そして、23日に四中全会が終わったら、一夜明けた24日にすぐに尖閣沖へと向かっている。
今回の四中全会(第20期中央委員会第4回全体会議)は、党や軍での権力闘争によって、波乱の展開となると予想されていた。
中には、「習近平(*)総書記が失脚する」「中央軍事委員会の首席の地位には張又俠(副主席)がつく」など、根拠の有る無しを問わず様々な憶測がとびかっていた。
(*)主な肩書きは3つ。中央委員会の総書記、党中央軍事委員会と国家中央軍事委員会の主席、国家主席。
開会直前の10月17日には、中国の国防部が、軍の最高指導機関である中央軍事委員会の何衛東(何卫东)副主席、苗華(苗华)委員ら高官9人に対して党籍剥奪の処分を決定したとの発表があったのでなおさらだった。これは異例な対応だった。この決定は四中全会で承認され、中央委員会からの除名も発表された。
この9人の中には、中国海警局(海警総隊)の上部組織である人民武装警察部隊の司令官だった王春寧(王春宁)も含まれている。(王春寧は数カ月前に失脚と見られている。今年7月に武警”司令員代理”が行政組織の発表に現れている)。
軍制服組トップ級が失脚 高官9人の党籍剥奪―中国:時事ドットコム
中国海警局にとっても他人事ではない。
2023年12月に習近平氏は、中国海警局(武装警察部隊 海警総隊)の東シナ海を管轄する東海海区の司令部を視察した。
今回、失脚が明らかになった何衛東(何卫东)や、東部戦区司令官だった林向陽(林向阳)、武警部隊司令官だった王春寧(王春宁)らが参加していた。武警政治委員の張紅兵(张红兵)や習近平の軍事面での「幕僚長」と言われた鐘紹軍(钟绍军)も失脚している可能性が指摘されている。
 (何衛東(何卫东))
(何衛東(何卫东))
【中国海警局】 習近平が中国海警局東海海区司令部を視察 記念撮影と参加した将官【写真】(追記あり) - pelicanmemo (2023-12-04)
中国海警局 カテゴリーの記事一覧 - pelicanmemo
Ads by Google
続きを読む